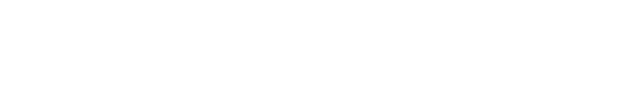抗うつ薬とは|効果・副作用・種類を解説
「抗うつ剤は飲んでも本当に大丈夫なの?」
「副作用が強かったり、やめられなくなったりしないのかな」
こんなご心配の声をききます。
抗うつ薬は、気分の落ち込みや意欲の低下などの症状をやわらげるために使われる薬です。
「怖い薬」というイメージを持たれがちですが、適切に使えば、安全性が高く、前向きな回復をサポートしてくれる“こころの味方”でもあります。
抗うつ薬の種類やはたらき、副作用や正しい使い方についてわかりやすく解説します。
抗うつ薬とは?種類と仕組みをやさしく解説
抗うつ薬は、気分の落ち込みや不安、意欲の低下などをやわらげるために使われる薬です。
脳の中では、「セロトニン」や「ノルアドレナリン」などの神経伝達物質が気分や意欲、喜びなどをコントロールしています。
しかし、うつ状態のときには、これらのバランスが崩れて、気分の落ち込みやイライラ、不眠などがあらわれると考えられています。
抗うつ薬は、神経伝達物質のはたらきを助けることで、こころの調子を整えていきます。
飲んだその日からすぐに変化があるというよりも、時間をかけてじわじわと回復していきます。
まずは、抗うつ薬が効く仕組み、それから具体的にどのような薬があるかを解説します。
抗うつ薬が効く仕組み
私たちの脳では、セロトニンやノルアドレナリンなどの神経伝達物質が、神経細胞どうしの情報伝達に関わっています。
健康な時は神経伝達物質のバランスや働きが保たれていますが、強いストレスがかかるなどバランスが崩れるようなことが起こると、神経伝達の働きが低下し、気分が落ち込んだりやる気がなくなったりします。
抗うつ薬は、神経細胞から分泌されたセロトニンやノルアドレナリンを脳内の必要なところに長くとどめる働きがあります。
その結果、脳内でこれらの物質が効果的に働くようになり、神経伝達のバランスが整っていきます。
これによって、気分の落ち込みや意欲の低下といった症状が、少しずつ改善されていきます。
代表的な薬の種類
抗うつ剤には、以下のような薬があります。[1]
| 分類 | よく使われる薬の一般名 (カッコ内は先発品) |
| SSRI (選択的セロトニン再取り込み阻害薬) |
|
| SNRI (セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬) |
|
| NaSSA (ノルアドレナリン作動性・特異的セロトニン作動性抗うつ薬) |
|
| S-RIM (セロトニン再取り込み/セロトニン受容体モジュレーター) |
|
それぞれの薬は違った方法でセロトニンやノルアドレナリンのはたらきを助け、脳内のバランスや環境を整えます。
抗うつ薬の効果|どんな症状にどう効くのか
抗うつ薬の効果について、どんな症状に効果があるか見ていきましょう。
抗うつ薬で改善が期待できる代表的な症状
抗うつ薬は、気分の落ち込みをやわらげるだけでなく、うつ状態にともなってあらわれるさまざまな症状に働きかける薬です。
こんなこともうつ病のサインです。
- 朝起きても布団から出られないほどのだるさ
- 好きだった音楽やSNS、テレビなどを「面白い」と感じられない
- 人と話すのが億劫で、LINEの返信すらつらい
- ずっと不安や焦りが続いて、落ち着かない
- 眠れない、夜中に何度も目が覚める
- 食欲がなく、何を食べても味がしない
- すぐ涙が出て、自分を責めてしまう
- 「いなくなった方がいいかもしれない」と考えてしまう
こうした症状は、脳内の神経伝達物質(セロトニンやノルアドレナリン)の乱れが関係していると考えられています。
抗うつ薬は、このバランスを整えることで、こころとからだの状態を少しずつ回復の方向へ導いていきます。
たとえば、薬が効いてくると、次のような変化を感じる方が多くいらっしゃいます。
- 一日中寝ていたのに、最近は朝に一度起きられるようになった
- テレビを見ても何も感じなかったのに、少しだけ笑える瞬間があった
- ずっとLINEを無視していたけど、今日は返信ができた
改善は一気に起きるものではなく、少しずつ・段階的に進んでいくのが特徴です。
一枚一枚薄紙をはがすように、回復していきます。
効果があらわれるまでの期間と目安
抗うつ薬の効果は、服用を始めてから2〜4週間ほどで少しずつあらわれます。
「すぐに元気になる」「毎日が楽しくなる」といった劇的な変化を期待していると、「効いていないのでは?」と不安になるかもしれませんが、人間も生き物なので、回復するとしてもそのプロセスに時間がかかります。
「良くなったり悪くなったりを繰り返しながら少しずつ調子の良い日が増えていく」というイメージを持っていただくと分かりやすいかもしれません。
「今日はちょっと気持ちが落ち着いている」「少し家事をやってみようかなと思えた」など、少しずつでも変化があれば回復の兆しです。
うつ病は、焦らずにゆっくりとこころのコンディションを整えていくことが大切です。
また、よくなっても症状のぶり返しを防ぐために、短くとも数ヶ月は薬を継続します。
また、薬で十分な効果が得られなかったり、副作用で薬が合わなかったりした場合は、薬を増やしたり切り替えたりしながら合う薬を探していきます。
不安や疑問があるときは、一人で抱えこまず気軽にご相談ください。
ご自分に合うペースで、ゆっくりと回復を目指していきましょう。
副作用が不安な方へ|よくある症状と対処法
抗うつ薬の代表的な副作用について、症状や対処法などを紹介していきます。
薬の効果や副作用には個人差があります。
抗うつ薬は、効果よりも先に副作用が出ることが多いので、この段階でつらくなってしまうこともありますが、たいていの副作用は、慣れていくので、生活に大きな支障がなければ続けていただきます。
副作用について、気になる点があれば一人で悩まずにご相談ください。
眠気、吐き気の場合
抗うつ薬の飲み始めは、眠気や吐き気が出る方もいます。
眠気や吐き気は、日にちが経つにつれて落ち着くことがほとんどです。
眠気が出た場合は、回復を助けるためにもゆっくり休みましょう。
慣れる様子がなかったり日常生活に支障が出るような場合はご相談ください。薬の変更や増量のペースを調整します。
つらさが続き副作用が強いと感じる場合
眠気や吐き気、口の渇き、気分の変化などがつらい場合は、ご自分の判断で薬をやめることはせず、必ずご相談ください。
とくに今まで飲んでいた薬を増やして副作用が強くなった場合、薬自体を急にやめてしまうと「中断症候群(離脱症候群・退薬症状)」が起こり、めまいや不眠が出る可能性があります。[2]
すぐに相談・受診いただきたい症状
次のような症状が出た場合は、すぐにご相談ください。[3]
- 手足の震えやからだのこわばり
- 発熱や動悸
- 強い不安、気分の波が激しくなった
抗うつ薬に関してよくある質問
抗うつ剤に関してよくある質問にお答えしていきます。
抗うつ剤の副作用にはどんなものがありますか
抗うつ薬は、正しく使えば安全性の高い薬ですが、飲み始めに眠気、消化器症状(吐き気・食欲不振)などの副作用が出ることがあります。
日数が経つにつれて落ち着く方が多いのですが、ひどくつらい場合はご相談ください。
また、薬で体調が安定していた方がいきなり薬をやめてしまうと「離脱症候群(中断症候群・退薬症状ともいいます)」が起こり、不安感の悪化やめまいなどがあらわれることもあります。
離脱症候群は薬をゆっくりと減らすことで予防できます。
薬の変更や中止は、焦らずにゆっくりと進めていきましょう。
抗うつ薬に依存性はありますか?
抗うつ剤に関して、いわゆる「依存性」の心配はほとんどありません。
依存性とは、薬を飲み続けないと心や体が正常に保てず、やめたくてもやめられなくなる状態を指します。
抗うつ薬は、アルコールやタバコなどと異なり、飲むと気持ちが良くなったり幸せな気持ちになったりする感じはありません。
また、薬に体が慣れて効かなくなる「耐性」もできにくいため、医師の指示のもとに使用すれば、多くの場合安全に服用できます。
ただし、いきなりやめると、神経伝達物質のバランスが崩れて「離脱症状(中断症候群)」が出る可能性がありますが、「依存」ではなく、急な変化による一時的な反応です。
ゆっくりと減らすことで、離脱症状のリスクは軽減できます。
抗うつ薬で認知症になることはありますか?
一部の抗うつ薬には、「抗コリン作用」という副作用により、認知機能に影響する可能性があります。[4]
当院ではリスクの高い高齢者の方にも比較的年齢の若い方にも認知症リスクの高い薬はほとんど処方していません。
抗うつ薬で感情がなくなることはありますか?
「抗うつ薬で感情がなくなる」ということは、基本的にはありません。
薬でロボットのようにコントロールされるイメージがあるのかもしれませんが、実際には、うつ状態の改善で再び感情が生き生きと感じられるようになることの方が多いです。
薬を飲んであらわれた気持ちの変化に不安がある場合は、遠慮なくご相談ください。
抗うつ薬は一生飲み続けないといけませんか?
抗うつ薬は、症状が落ち着いて再発のリスクが低い状態になってから、徐々に減らしていくのが基本の飲み方です。
「薬をやめたい」と思うあまり、ご自分の判断でやめてしまうと再発のリスクが高まります。
治療のゴールは「薬をなくすこと」ではなくて、「快適で人間らしい生活ができること」です。
症状がよくなって、再発のおそれが少なくなったら、少しずつ「この量でも再発はしないかな」と確かめながら薬を減らしていきます。
薬を卒業できるまで、ゆっくりと向き合っていきましょう。
抗うつ薬に市販薬や代替手段はありますか?
現在、日本では抗うつ薬として認可された市販薬は存在しません。
抗うつ薬が必要な場合は、必ず医師の診察を受けて処方を受ける必要があります。
「気分を明るくする」「やる気を出す」などのサプリメントや市販薬はメカニズムが異なるため、ご自分の判断で抗うつ薬の代わりにするのは避けましょう。広く効果をみとめられた薬で適切な治療をうけることが速やかな改善につながります。
当院ではよりきめ細かな治療のため、カウンセリングと薬物療法を組み合わせておこなうこともあります。
一人ひとりの症状や回復状態によって合う治療法は異なるため、気になる点はご相談ください。
抗うつ薬はお酒(アルコール)といっしょに飲んでもいいですか?
抗うつ薬を飲んでいる方は、飲酒を避けてください。
アルコールを飲むと一時的に気分が高揚して楽しい気持ちになりますが、長期的にはうつ病を悪化させる方向にはたらくからです。
酔いから覚めると飲む前よりも気持ちが落ち込みやすいこと、また安全性の面からもお酒を飲むと薬の副作用が強く出やすいため飲酒は控えてください。
抗うつ薬を上手に利用していきましょう
抗うつ薬は、「怖い」「依存しそう」といったイメージを持たれることもありますが、適切使えば、うつ症状の改善を支えてくれる心強い存在です。
種類や効果、副作用は人によって異なるため、不安なことがあれば一人で悩まずに、ご相談ください。
あせらず、少しずつ、自分のペースで回復を目指していきましょう。
参照文献:
[1]今日の治療薬2025 南江堂
[2]日本うつ病学会ガイドライン
https://www.secretariat.ne.jp/jsmd/iinkai/katsudou/data/20240301.pdf
[3]重篤副作用疾患別対応マニュアル セロトニン症候群
https://www.pmda.go.jp/files/000240114.pdf
[4]重篤副作用疾患別対応マニュアル 薬剤性せん妄
https://www.pmda.go.jp/files/000245273.pdf