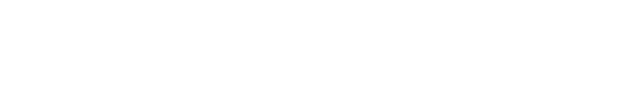ADHDと治療薬|コンサータ・ストラテラ・インチュニブの効果
「集中力が続かない」「うっかりミスが多い」「じっとしていられない」「ついカッとなってしまう」「いつまでも考え続けて決められない」「うっかり余計なことを言ってしまう」
そういった症状によって日常生活や仕事に支障が出ている場合、ADHD(注意欠如・多動症)の特性によるものかもしれません。
ADHDは、自閉スペクトラム症(ASD)、学習障害(LD)などと並ぶ発達障害の一種です。本人の努力不足や性格の問題というより、脳の機能的な特性によるものといえるでしょう。
困りごともある一方で決断力、行動力、自由な発想など魅力的な面を持ち合わせている方も多くいらっしゃいます。
適切な治療を受けることで、ご自身の能力が発揮しやすくなる可能性があります。
ADHD治療薬の役割や効果、薬との向き合い方について解説します。
ADHDを理解しよう
ADHDは脳の中枢神経系における「実行機能系」と「報酬系」という2つの機能がうまく働いていないことが知られています。
脳の働き「報酬系」と「実行機能系」
2つの機能のはたらきや、ADHD症状との関係について、以下にまとめました。
| はたらき | うまくはたらかないことで起こる症状 | |
| 実行機能系 | やるべきことを整理して、計画的に実行する |
|
| 報酬系 | 「嬉しい」「楽しい」などと感じる |
|
なお、実行機能系は脳の「前頭前野」という部分、報酬系は「眼窩前頭皮質」「腹側線条体」「前部帯状回」という部分が関係しています。
これらの部分がうまく働かない結果、ドパミンやノルアドレナリンといった「神経伝達物質」のはたらきが不十分になり、ADHDの症状があらわれると考えられています。
ADHD治療薬の役割と考え方
ドパミンやノルアドレナリンは、脳の覚醒を維持するために大切な神経伝達物質ですが、
ADHDではドパミンやノルアドレナリンが十分にない、またはシグナルが弱い状態と考えられています。
アトモキセチン・メチルフェニデートが効く仕組み
脳内では、ドパミンやノルアドレナリンといった神経伝達物質は「トランスポーター」という神経伝達物質の乗り物によって神経から神経へ受け渡され、情報をやり取りしています。
しかし、ときには後ろの神経に届かずに、トランスポーターによって前の神経に戻されてしまうことがあります。そうすると情報はうまく伝達されません。
アトモキセチンやメチルフェニデートは、このトランスポーターの働きを調整して神経伝達物質が必要なところに長くとどまらせ、脳を覚醒させます。
メチルフェニデートが中枢刺激薬と呼ばれるのも、こういう仕組みがあるからです。
グアンファシン(インチュニブ)が効く仕組み
神経伝達物質は、伝達された後にどれだけ働いてくれるかも大切です。
ADHD治療薬のなかでもグアンファシンは、「α2A受容体」という部分に作用して、ノルアドレナリンのシグナルのはたらきを強めます。[1]
α2Aアドレナリン受容体は、イライラや衝動性などの原因となりえる「交感神経系」のはたらきを緩和する効果があります。
グアンファシンがα2A受容体に作用する結果、衝動性や注意機能のコントロールに関わる脳の「前頭前野」の働きを改善すると考えられています。
※ノルアドレナリンはα、βという2種類の受容体に作用して、脳の神経伝達、血圧、痛みの感覚、ホルモン分泌などの調整に関わる神経伝達物質です
詳しい脳のしくみは分かっていない部分もありますが、さらなる病気の解明や治療薬の開発に向けて、日々研究が進められている分野です。
中枢刺激薬|メチルフェニデート(コンサータ)・リスデキサンフェタミン(ビバンセ)の特徴と効果
メチルフェニデートとリスデキサンフェタミンの2つは、「中枢刺激薬」という分類のADHD治療薬です。
この2つは、成分が同じもしくは似ている別の薬が乱用された事例が過去にあったり、指示された量や飲み方を守らないと依存のリスクがあったりします。
そのため、あとで詳しく紹介する「ADHD適正流通管理システム」による管理がされており、「適正流通委員会」という機関でも薬の処方や受け渡しを確認しています。
2つの薬の特徴や効果について、説明していきます。
メチルフェニデート徐放剤(コンサータ)
コンサータは、「ドパミントランスポーター」と「ノルアドレナリントランスポーター」という部分に作用して、ドパミン・ノルアドレナリンが再取り込みされるのを防ぐ薬です。
脳内のうち前頭前野という部分にあるドパミンとノルアドレナリンの濃度を高めることで、ADHD症状をやわらげます。
ノルアドレナリンにも作用しますが、ドパミンの作用をしっかりと高めてくれるのがコンサータの特徴です。[1]
また、「報酬系」という「嬉しい」「やる気が出る」などを感じる脳の仕組みを高める作用があるため、コンサータを服用しながら生活面を整えていくケースもあります。
代表的な副作用は、頭痛や腹痛、不眠、食欲低下、情緒の不安定などです。頭痛や腹痛は薬がからだに馴染むと治まるケースが多いのですが、食欲低下が続く場合はご相談ください。
また、ドパミンやノルアドレナリンには、神経を興奮させる作用もあるため、飲むタイミングが午後にずれてしまうと不眠が起こりやすくなります。
実はコンサータは、ナルコレプシーという日中の強い眠気を感じる病気の治療に使われる「リタリン」という薬と同じ成分です。
コンサータの方が一日中おだやかに作用するように薬の錠剤が工夫されているのですが、神経興奮作用が寝るタイミングであらわれてしまうと眠れなくなる可能性があるのです。
なお、錠剤はかみ砕いたり、割ったりすると、薬がゆっくりと効くしくみがうまく働かない可能性があります。そのまま水やぬるま湯で服用してください。
また、薬を覆っている膜が便に排出されるケースがありますが、問題はありません。
薬には合う・合わないがあるため、気になる点は早めにご相談ください。
リスデキサンフェタミン(ビバンセ)
2025年5月現在、ビバンセが保険診療に適用されるのは、6歳から17歳までの患者様のみです。
そのため、基本的に保険診療において18歳以上の方に新しく処方をすることはありません。
ビバンセは、リスデキサンフェタミンという成分を含むADHD治療薬です。
d-アンフェタミンという成分に工夫をして、1日1回の服用で効果が続くように工夫されています。
ビバンセも、コンサータのように「ドパミントランスポーター」と「ノルアドレナリントランスポーター」に作用して再取り込みを防ぎます。
さらに、シナプスからドパミン・ノルアドレナリンが遊離するのを助ける作用もあります。
その結果、ドパミン・ノルアドレナリンの濃度が高まり、ADHD症状がやわらぐのです。
基本的には、一番最初に選ばれることは少なく、ほかの薬で十分な効果が得られなかった際に使用を検討する薬です。[2]
おもな副作用は、コンサータと同じく食欲低下や不眠、頭痛、吐き気などです。どれも飲みはじめに現れやすく、しばらくすると治まるケースが多く見られます。[1]
食欲低下については、薬を飲む前に朝食をとる、間食や夜食を追加する、夕食の時間を薬の効果が切れる頃まで遅くするなどで対応できる場合もあります。
不眠についてはコンサータと同様に、午後以降に服用がずれないように注意することも大切です。
薬の副作用がつらい、気になる症状があるなどの場合はご相談ください。
コンサータ・ビバンセを処方するしくみ
コンサータとビバンセは、薬が正しく患者さんに渡るように「ADHD適正流通管理システム」によって流通が厳しく管理されています。
アトモキセチン・グアンファシンはどの医療機関でも処方ができ、在庫があればどの薬局でも調剤を受けられます。しかし、コンサータとビバンセを処方・調剤できるのは、研修を受けて許可を得た医師・薬剤師のみです。
患者様が処方を受けるには、ADHDの診断と診断の根拠になる客観的な資料(通知表、母子手帳等)が必要になります。処方が必要と判断されたら流通システムに登録して「患者カード」が発行されます。
カードは毎回の処方時に必要となります。受診の際は、患者カードと身分証明書を毎回ご持参ください。薬局でも必要です。
非中枢刺激薬|アトモキセチン(ストラテラ)・グアンファシン(インチュニブ)の特徴と効果
ADHD治療薬には、脳の興奮を直接高めずにやさしく整えるアトモキセチン・グアンファシンという薬もあります。
コンサータやビバンセよりは穏やかに効くケースが多いのですが、依存のリスクが低いため管理システムを通す必要がありません。
2つの薬について説明していきます。
アトモキセチン(ストラテラ)
アトモキセチンは、ノルアドレナリンの再取り込みをする「ノルアドレナリントランスポーター」のはたらきを抑えることで、脳内の情報伝達を改善する薬です。
この薬はコンサータとビバンセと異なり、ドパミントランスポーターにはほとんど作用しません。
そのため、「楽しい」「嬉しい」などの感情に関わる報酬系へ直接的な作用は、穏やかだとされています。
ただし、「実行機能系」に関わる前頭前野など一部の脳部位では、ノルアドレナリントランスポーターがドパミンの調節にも関わります。
そのため、「順序だてて取り組む」「気を散らさずに物事に取り組む」などの実行機能については、ドパミンとノルアドレナリンの両方のはたらきを助ける効果が期待できます。
また、個人差がありますが、アトモキセチンは数週間かけてゆっくりと効果が出てきます。
おもな副作用は、食欲減退や吐き気、眠気、頭痛などです。慣れてくるケースも多いのですが、つらい場合はご相談ください。
グアンファシン(インチュニブ)
グアンファシンは、脳内の「α2Aアドレナリン受容体」という部分に作用して神経伝達シグナルを強めることで、ADHD症状をやわらげる薬です。
ほかの3種類(コンサータ・ビバンセ・アトモキセチン)と異なり、ドパミンやノルアドレナリンの濃度を上げずに実行機能を高めてADHD症状をやわらげます。なお、報酬系への作用は少ないとされています。[1]
基本的な飲み方は1日1回で、おもな副作用には、眠気、頭痛、血圧低下などです。
神経の興奮を抑える効果があるため、ほかの薬よりも眠気が出やすい傾向があります。
眠気や頭痛は慣れるケースが多いのですが、日常生活に支障が出る場合は飲むタイミングや薬自体の変更を検討する場合もあります。
また、1日1回で薬が効くよう工夫されているため、錠剤を割ったりかみ砕いたりせずに、そのまま服用してください。
薬について気になる点は、気軽にご相談ください。
ADHD治療薬の使い分け
ADHD治療薬は、薬の効くメカニズムや効果の傾向が異なります。
どの薬を選ぶかは、現在の困りごとやライフスタイル、副作用の出やすさなどで決まります。
症状によって異なりますが、以下のような使い分けをされるケースが多く見られます。
| メチルフェニデート徐放剤(コンサータ) |
|
| リスデキサンフェタミン(ビバンセ) |
|
| アトモキセチン(ストラテラ) |
|
| グアンファシン(インチュニブ) |
|
最初は、アトモキセチン・グアンファシンの2種類から薬を1つ選びます。
眠気や気持ち悪さが出ないように最初は少なめの量から始めて、少しずつ様子を見ながら効果が得られる量まで増やしていきます。
しかし、薬の量を増やしても十分な効果を得られなかったり、副作用で薬が合わなかったりした場合は、別の薬に変更し、また少ない量から始めていきます。
それでも期待した効果が得られなかった場合は、コンサータのへの変更、または追加を検討します。
薬の効果には個人差が大きいため、服用してみてはじめて分かる部分が少なくありません。
焦らずに、合う治療法をいっしょに探していきましょう。
大人のADHD治療薬に関してよくある質問
大人のADHD治療薬に関してよくある質問にお答えします。
ADHDは薬で治りますか?
ADHDは脳の特性の一つで、裏表のない発言や、行動力など、独特の魅力を持っている方もたくさんいらっしゃいます。
治す・克服するというより、不便なところは折り合いをつけて、自分らしいままで社会生活を送れるようにすることも目標にするといいでしょう。
薬は、不注意、多動性、衝動性といった症状をコントロールし、日常生活での困りごとを軽減することに役立ってくれます。
「薬は、ADHDをコントロールするサポート役」と考え、上手に利用していきましょう。
ADHD治療をしながらの妊娠は可能ですか?
ADHD治療をしながら、赤ちゃんを出産される方もいらっしゃいます。
産科・精神科で連携を取りながら、安全に出産できるようにサポートしていきます。
ただし、グアンファシンは妊娠中の方には使用できないため、ほかの薬への変更をおこないます。
症状の重さや妊娠経過に応じて、一人ひとりに合わせた治療法を検討していきます。
妊娠中のお薬については、以下の記事もぜひご覧ください。
理解と納得感が前向きなADHD治療のカギです
ADHD治療薬は、ADHDに伴う様々な困りごとを軽減し、より自分らしい生活を送るための大きな助けとなります。
当院では、患者さん一人ひとりの状況に合わせた治療法を一緒に見つけていくことを大切にしています。
ADHDの特性と上手く付き合い、より充実した毎日を送るために、薬を上手に活用していきましょう。
当院では、15歳以上の患者様のADHD治療をおこなっております。じっくりと時間をかけた発達障害の心理検査(自費)もおこなっており、より安心して生活していくためのお手伝いをいたします。
診療は予約制となっております。詳しくは以下のページをご参照ください。
参考文献:
[1]注意欠陥・多動症-ADHD-の診断・治療ガイドライン第5版 株式会社じほう
[2]ビバンセ|添付文書
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/400256_1179059M1024_2_01#HDR_Warnings